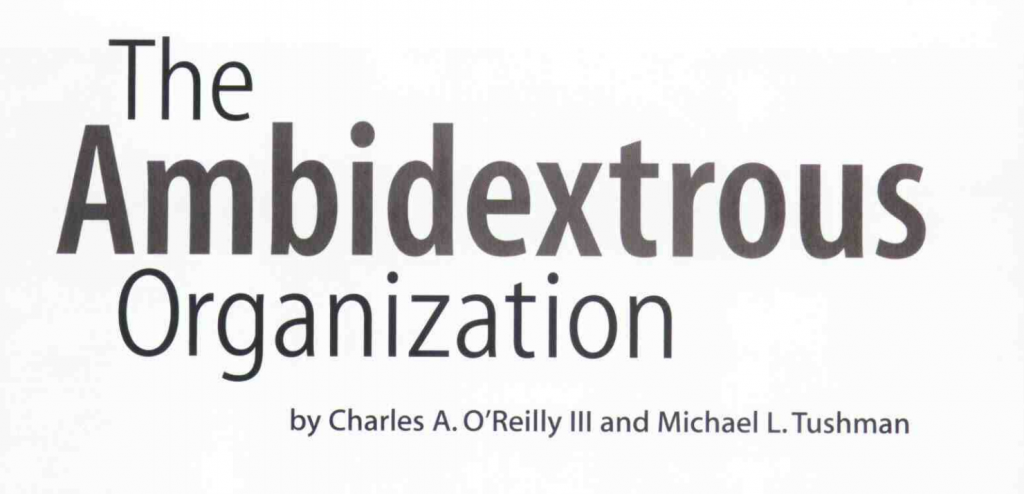
Contents
なぜ大企業はイノベーションを起こせなくなるのか
一般的によく知られるイノベーションのジレンマとは、企業が合理的判断の結果として既存事業への投資判断を続けた結果、他社のイノベーションの前に競争優位を失う現象を説明したもので、1997年にクリステンセン教授が提唱しました。ポイントは「合理的判断の結果」という部分です。既存商品やサービスを、顧客の声に耳を傾け改善し、見返りの不確かなことにはコストをかけないという、一見企業としては正しい行動が世の中に求められないものを作ることに繋がっていくのです。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。
その理由は3つあります。1つ目は持続的な投資判断。2つ目は仕様と需要の逆転。そして3つ目が新しい価値観の登場です。携帯電話を例に見ていきましょう。
同じ事業に継続投資してしまう
企業は常に成長を求められます。そのため、確実性のある事業への投資が優先されます。携帯電話が売れたのなら、翌年それを改良したものを出せば更に売れるだろうと考え、製品の改良を進めます(中計の数字は必ず前年伸びがでてるでしょ?)。このような既存事業の発展を持続的イノベーションと呼びます。事業の確実性という判断基準がある限り、海の物とも山の物ともつかない新規事業は投資対象になりにくいのです。
いつの間にかユーザーが不要だと思うものを作っている
この結果、携帯電話は様々な機能を持つようになります。しかし、一般消費者はもはやそこまでの性能を求めなくなります。未来を告げた革新的なデバイスは、もはやどんな機能があるかさえもわからない難解な機械になります。今までは需要に対してスペックアップしていったものが、いつの間にか望まれていないレベルに到達するのです。
全く違う価値観のプロダクトに太刀打ちできなくなる
そんな時、それまでの携帯電話とは一線を画する商品が登場します。スマートフォンです。そんな使いづらいものは売れないと言われたのもつかの間、ものの数年でスマートフォンは既存の携帯電話を駆逐してしまいました。スマートフォンはそれまでの携帯電話とは異なる操作性や自分でアプリを追加するという拡張性を全面に押し出し、これまでにない価値をユーザーに提供したのです。これが有名な破壊的イノベーションです。
両利き経営とは何か
既存の携帯電話のような事業推進のあり方は知の深化(Exploitation)と呼ばれます。そしてもう一方の考え方が知の探索(Exploration)です。この考え方は1991年にマーチが提唱したもので、近年では早稲田大学の入山先生が紹介したことで一般的にも知られるようになりました。マーチはすでに、この段階で企業は知の深化に偏りがちなことを指摘しています。
この考え方に立脚し、両利き経営(Ambidexterity)が重要だと説いたのがタッシュマンとオライリーです。企業はこの双方をうまく使い分けて経営をしなければならないという主張です。
二人は新規事業に取り組む35の企業を調査し、そこから組織形態を4つに分類します。
- 既存部門内で新規事業に取り組むケース…7件
- 既存部門を横断する部門を置くケース…9件
- 独立した企画部門を新設するケース…4件
- 独立した組織(企画・開発から実行部門まで)をまるごと設置するケース…15件
4のケースがまさに両利きの組織(Ambidextrous Oraganization)です。このタイプでは両組織を統括する責任者を置きます。そして、トップレベルマネジメントにおいて戦略的な統合をおこないます。つまり、日々のオペレーションこそ全くの別組織として分離しますが、資源配分や事業間シナジーなど調整は経営トップがおこなうということです。これにより、既存事業は結局事業化されない新商品公募をしなくていいし、新規事業は意思決定の遅い上司に悩まされることもないというわけです。
この時、実に9割以上がプロジェクトを成功させたと報告されています。同時に、1〜3の企業が両利き組織に変更した場合、8社中7社のパフォーマンスが改善し、逆の場合はパフォーマンスが落ちたとも。
興味深いのは、両利きの組織である場合はすべての企業で既存事業部門のパフォーマンスも向上したことです。逆にそれ以外のケースでは、既存部門のパフォーマンスが低下しました。両利きの組織はイノベーションの取り組みとして取り上げられる事が多いのですが、既存事業の継続性を毀損しないというところに大きな価値があると言えます。
両利き経営に必要な3つのポイント
特に取り上げられているのが、USA Today と チバビジョン(現ノバルティス)です。この2つの企業のケースを通じてタッシュマンとオライリーは次の3つの要素が両利き経営に必要であるとしています。
責任者自身が両利きであること
既存事業と新規事業の間では、常に様々なトレードオフが起こります。コストカットの一方で試作品の莫大な予算を取らなくてはならなかったり、厳格な手続きを要求する仕事もあれば暗中模索の中で「えいや」の決断も求められます。両事業のニーズを敏感に察知し、「常に矛盾する状況」に処することができる人が責任者でなくてはなりません。つまり、責任者を適当に選んだら(特に既存事業の叩き上げでそれしか知らないような人)、その時点で改革は失敗します。
どんなときも両利きに振る舞うこと、それを奨励すること
あらゆるシーンで、組織を両利きに駆動させることを最優先にしなくてはなりません。両企業のケースでは、CEOが改革に反対するボードメンバーに退職を勧告しています。また、新たな取り組みに対する報奨制度を導入するなど、組織全体が両利きになるための仕組みづくりもおこなっています。お題目としてではなく、人も仕組みも変革する。このようにして責任者が行動してくことが重要です。
明確なビジョンを提示する
USA Todayは「Network Strategy」チバビジョンは「Healthy Eyes for Life」という、明文化をもって従業員に新たな企業ビジョンを提示しました。これにより、既存組織、新規組織それぞれの従業員が自分たちの存在意義や価値を理解します。双方の事業があって初めて実現できるビジョンが、組織の変革を表す何よりのアピールでありメッセージになるのです。
ボトムアップで両利き組織は成り立つか?
これまで見てきたようにタッシュマンとオライリーは、強力なマネージャーによる既存、新規の両部門を見据えた舵取りが必要だとしています。そのために、事例として上げられた2社はいずれもドラスティックな改革を実行しました。しかし当然ですが、このような改革は簡単ではありませんし、何よりCEO(あるいは実行責任者)の属人性に依存するところが大きいのが難点です。事実、「そのような人材は稀だ」とも述べられています。
冒頭のクリステンセンはジレンマを解消するためには新規事業のチームを既存事業とは分離し、独立した扱いにすべきだとしました。この議論は上記のような経営トップによる統合までは踏み込まなかったわけですが、日本企業にはこのような「出島戦略」止まりのケースは少なくありません。つまり、◯◯新規事業室や、オープンイノベーション推進室などが立ち上がるものの、当のメンバーは何をしていいかわからないという状態です。
そこで私は、ボトムアップから生まれる両利き組織こそが、これから求められるものだろうと考えています。昔からヤミ研と呼ばれる自主活動や、昨今熱を帯びている若手の有志団体のような実践共同体の活動成果を企業がうまく取り入れることができれば、新しい形での両利き組織が作られるのではないでしょうか。
この話はまた別の機会に。